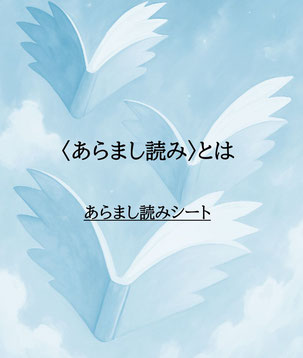〈あらまし読み〉―理解力と対話力を高める読書術―
〈あらまし読み〉とは、10代の児童・生徒・学生を対象に、新書などの情報読書に限定して、「本の外側」「目次」「序章」「興味」に注目した俯瞰的・効率的な読みの方法であり、自分の課題について深く考えるための準備読書(トップダウン読解)として設定したものです。3冊以上の〈あらまし読み〉を手がかりに、2度読み、3度読み(ボトムアップ読解)をしながら「比較レポート」というアウトプットを目指す方法をお勧めしています。このような読書から、幅広い知見を広げ、自分の課題について考えていきます。自分の考えの整理をした結果を、「レポート作成」しましょう。
参考資料リンク:「学校図書館」(公益社団法人全国学校図書館協議会)6回連載 2025.04-09 [〈あらまし読み〉体験をしよう]
牧恵子「〈あらまし読み〉ワークショップを継続して聞こえてきた声」『学校図書館』2025年8月号(
牧恵子「さぁ、〈あらまし読み〉体験をはじめよう!」『学校図書館』2025年9月号(
あらまし読み実践地図
〈あらまし読み実践地図〉は以下の分類を色別しています
・ ワークショップや授業の報告(黒)
・ 研修会報告(紫)
・ 出版・実践報告論文(赤)
・ 研究者からの被引用(黄)
・ 企画展示(橙)
・ 受賞(赤)
関連リンク
愛知教育大学附属図書館
https://www.auelib.aichi-edu.ac.jp/
日本文学アクティブラーニング研究会
https://nihonbungakual.wixsite.com/koten
オフィス みちねこ